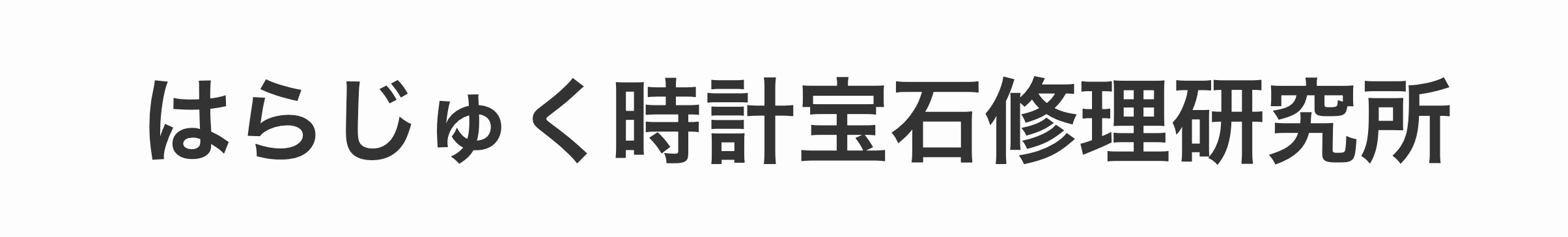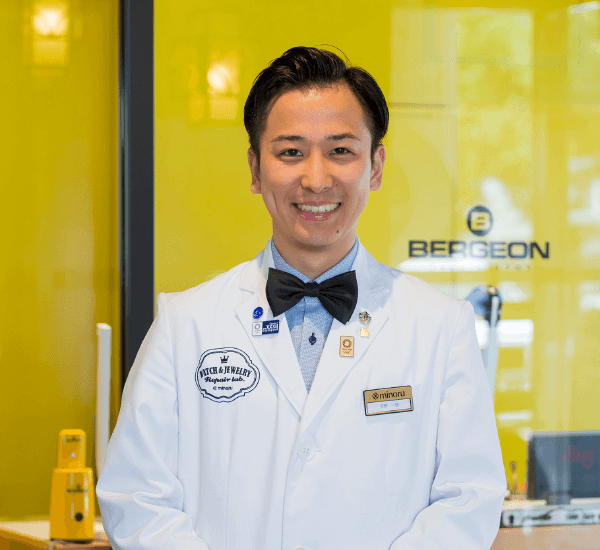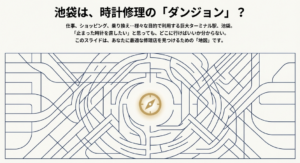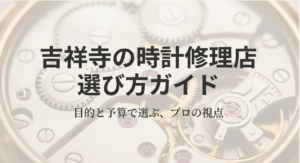時計の自動巻きが止まる原因は?対処法と修理を解説

こんにちは。はらじゅく時計宝石修理研究所、店長の天野 一啓です。
「時計の自動巻きが止まる」と検索されたということは、愛用されている時計の調子が悪くてご心配なことと思います。毎日使っているのにすぐに止まるようになったり、時間が遅れるようになったり、止まったまま放置してしまったり。もしかして故障かな?と不安になることもありますよね。デスクワークで着用時間が短いのが原因なのか、それともゼンマイの巻き上げ不足や、内部の油切れ、ローターの巻き上げ効率の低下といった内部の問題なのか。リューズの巻き方が分からない、という方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、自動巻き時計が止まる主な原因から、ご自宅でできる簡単な対処法、そして専門的な修理が必要なケースまで、分かりやすくお話ししていこうかなと思います。
東京・渋谷エリアで修理をお考えなら、JR原宿駅から徒歩1分とアクセス抜群の「はらじゅく時計宝石修理研究所」にご相談ください。国家資格を持つ修理技能士が、あなたの愛用の時計を丁寧に診断し、最適なメンテナンスをご提案します。他店で断られた修理にも対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
この記事でわかること
- 自動巻き時計が止まる主な原因
- 止まった時に自分でできる対処法
- 時計を長持ちさせる正しい保管方法
- 専門的な修理が必要な症状の見分け方
時計の自動巻きが止まる主な原因

自動巻き時計が止まると、すぐに「故障かも?」と心配になるかもしれませんが、実は単純な理由であることも多いんです。まずは慌てず、主な原因から探っていきましょう。
止まる原因はエネルギー不足?
自動巻き時計が止まる原因として、一番多いのは「ゼンマイの巻き上げ不足」ですね。これは故障ではありません。
自動巻き時計は、腕の動きで内部の「ローター」という半月状の重りが回転し、それがゼンマイを巻き上げる仕組みです。ですが、最近はデスクワークが中心の方も多く、時計を着けていても腕の動きが少ないと、ローターが十分に回らないことがあるんです。
消費されるエネルギーが、巻き上げられるエネルギーを上回ってしまうと、パワーリザーブ(蓄えられた動力)が徐々に減って、やがて止まってしまいます。一般的には1日に最低でも8時間から10時間の着用と、ある程度の活動量が必要と言われたりしますね。
巻き上げが不十分だと、時間が遅れがちになることもあるので、「最近なんだか遅れるな」と感じる場合も、エネルギー不足を疑ってみると良いかもしれません。
自動巻きはどれくらいで止まる?
これは、時計の「パワーリザーブ」によりますね。パワーリザーブとは、ゼンマイが最大まで巻き上げられた状態から、時計を外して置いておいた時に動き続ける時間のこと。車でいう燃料タンクの容量みたいなものです。
標準的なモデルだと、だいたい36時間から48時間(1日半〜2日)くらいが多いかなと思います。なので、例えば金曜日の夜に時計を外して週末使わないと、月曜日の朝には止まっている、というのはごく普通の現象ですね。
最近は技術も進んで、72時間(3日間)以上の「ロングパワーリザーブ」を持つモデルも増えてきました。これなら週末外しても月曜まで動いてくれるので、便利になったなと感じます。
止まるのは良くないことか
「時計を止めちゃいけない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、止まること自体は時計にとって特に悪いことではありません。
パワーリザーブが切れて停止するのは、設計上も想定されている正常な状態です。車を毎日動かさなくても壊れないのと同じような感じですね。
むしろ、時計を毎日24時間動かし続けると、それだけ部品は摩耗していきます。使わない日に時計を休ませることは、部品の摩耗を抑えるという意味では、メリットと考えることもできると思います。
止まった時のリューズ巻き上げ方法
止まってしまった時計を再び動かす時は、腕に巻いて振るだけではエネルギーが足りないことが多いです。そんな時は、手動でリューズを巻いてあげるのが確実ですね。これを「ジャンプスタート」と考えると分かりやすいかもしれません。
安全な手動巻き上げの手順
- リューズのロックを解除する(ねじロック式の場合)
ダイバーズウォッチなどに多い「ねじロック式リューズ」は、まずリューズを手前(反時計回り)に回してねじ込みを解除します。ポンと少し飛び出す感触があればOKです。 - ゼンマイを巻き上げる
ロックが解除された位置(または非ねじロック式の場合はそのままの位置)で、リューズを奥(時計回り)にゆっくり回します。 - 巻き上げ回数の目安
完全に止まった状態からは、だいたい30回から40回ほど巻き上げれば、安定して動き出すのに十分な動力が蓄えられます。 - リューズを元に戻す
巻き上げたら、ねじロック式の場合はリューズをケースに軽く押し込みながら奥(時計回り)に回し、しっかり締めてください。これで防水性も保たれます。
自動巻き時計は、手巻きと違ってゼンマイが最大まで巻かれても「巻き止まり」がありません。「スリップ機能」といって、それ以上巻いても力が逃げるようになっているので、無理に巻きすぎる心配はしなくて大丈夫ですよ。
使わない時の正しい保管方法
自動巻き時計は精密機械なので、保管場所もちょっとだけ気にしてあげると長持ちにつながります。
一番気をつけたいのは「磁気」と「湿気」ですね。
- 磁気: スマホ、パソコン、タブレット、バッグの留め具など、磁気を発するものの近くに置くのは避けましょう。時計の心臓部が磁化すると、時間が大きく進んだり、止まったりする原因になります。
- 湿気: 防水時計でも、リューズがしっかり締まっていないと湿気が入ることがあります。また、パッキンは年々劣化するので、湿気の多い場所(洗面所など)に置きっぱなしにするのはおすすめしません。
ワインディングマシーンは必要?
時計を自動で回してくれるワインディングマシーンですが、これは「必需品ではない」と私は思います。常に動かし続けることで部品の摩耗を早める可能性も指摘されていますし、何よりモーターから磁気が発生するリスクもあります。
複数の時計を持っていて、日付合わせが面倒な複雑な時計(永久カレンダーとか)をお持ちなら便利かもしれませんが、そうでなければ無理に使う必要はないかなと思います。数ヶ月以上使わない場合でも、1〜2ヶ月に一度、リューズでゼンマイを巻いて半日ほど動かしてあげるだけで十分ですよ。
東京・渋谷エリアで修理をお考えなら、JR原宿駅から徒歩1分とアクセス抜群の「はらじゅく時計宝石修理研究所」にご相談ください。国家資格を持つ修理技能士が、あなたの愛用の時計を丁寧に診断し、最適なメンテナンスをご提案します。他店で断られた修理にも対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
時計の自動巻きが止まる時の修理

エネルギー不足でもないのに止まる場合、内部の機械的な問題が隠れているかもしれません。ここでは、修理が必要なケースや、ご自身での対処のリスクについて見ていきましょう。
時計修理を自分で行うリスク
最近はネットで情報が手に入るので、「自分で修理できないか?」と考える方もいるかもしれません。ですが、これは非常にリスクが高いので、避けた方が賢明です。
例えば、磁気帯びをチェックするくらいなら方位磁石でできますが、市販の磁気抜き器は効果が不十分だったり、逆に磁気を強めてしまったりする可能性もゼロではありません。
裏蓋を開けるのは絶対にNGです!
最も危険なのは、裏蓋をご自身で開けてしまうことです。専用の工具なしで開けるとケースに傷がつくだけでなく、閉める時に防水性を保てなくなります。
なにより、目に見えない小さなホコリがムーブメント内部に入るだけで、数年後に致命的な故障を引き起こす原因になります。時計修理は、チリひとつないクリーンな環境で行う専門的な作業なんです。
専門的な修理が必要な症状
以下のような症状が出たら、ご自身で対処しようとせず、専門の修理店に相談することをおすすめします。
- 手動でゼンマイを30〜40回巻いても、全く動き出さない。
- 動き出しても、着用しているのに数時間でまた止まってしまう。
- 時計を振ると、内部から「カタカタ」「ガリガリ」といった明らかな異音がする。(ローターが緩んでいるか、部品が外れているかも)
- 毎日、だいたい同じ時刻になると時計が止まる。(歯車に問題があるかも)
- リューズを巻く時に、ザラザラした感触や異常な重さ、または逆にスカスカで手応えがない。
- 風防(ガラス)の内側が曇ったり、水滴がついたりしている。(水が浸入しています)
これらの症状は、内部の部品が摩耗したり、破損したりしているサインかもしれません。
オーバーホールにかかる費用
時計の内部的な問題の多くは、「オーバーホール(分解掃除)」というメンテナンスで解決できます。機械式時計は、3〜5年に一度のオーバーホールが推奨されていますね。これは、内部の潤滑油が時間とともに劣化してしまい、部品の摩耗を引き起こすのを防ぐためです。
費用については、ブランドや時計の機構(クロノグラフなど)、部品交換の有無によって大きく変わってきます。あくまで一般的な目安ですが、国産ブランドで2万円台から、スイス製のラグジュアリーブランド(ロレックスなど)になると5万円以上、複雑なものだと10万円を超えることもあります。
オーバーホールを怠って油が切れたまま使い続け、部品が広範囲で摩耗してしまうと、時計のオーバーホールの値段・相場に加えて高額な部品交換代がかかってしまうこともあります。
ここに記載している費用は、あくまで一般的な目安の範囲です。時計の状態や必要な部品交換によって、実際の金額は変動します。正確な費用については、必ず修理店で見積もりを取って確認するようにしてください。
カルティエの修理も対応可能
当店、はらじゅく時計宝石修理研究所では、ロレックスやオメガはもちろん、カルティエのようなブランドウォッチの修理も数多く承っています。
カルティエは自動巻きモデルもありますが、「タンク」や「パンテール」などクオーツ(電池式)モデルも多いですよね。クオーツ時計も、止まった原因が単なる電池切れではなく、内部の回路や機械部分(歯車)の油切れであることもあります。
「この時計、直るかな?」と不安な場合でも、お気軽にご相談いただければと思います。当店でのカルティエの時計修理(オーバーホール/電池交換)などもサイトでご紹介していますので、参考にしてみてください。
時計の自動巻きが止まる悩み相談
ここまで、時計の自動巻きが止まる原因や対処法についてお話ししてきました。止まる原因は、単純なエネルギー不足から、磁気帯び、そして内部部品の劣化まで、本当にさまざまです。
ご自身で「これはエネルギー不足だな」と判断できるうちは良いですが、リューズを巻いてもすぐ止まったり、異音がしたりする場合は、無理に使い続けたり、自分でなんとかしようとしたりせず、時計の専門家に相談するのが一番の近道ですね。
大切な時計を長く愛用するためにも、早めの点検・修理を心がけるのが良いかなと思います。
東京・渋谷エリアで修理をお考えなら、JR原宿駅から徒歩1分とアクセス抜群の「はらじゅく時計宝石修理研究所」にご相談ください。国家資格を持つ修理技能士が、あなたの愛用の時計を丁寧に診断し、最適なメンテナンスをご提案します。他店で断られた修理にも対応可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。